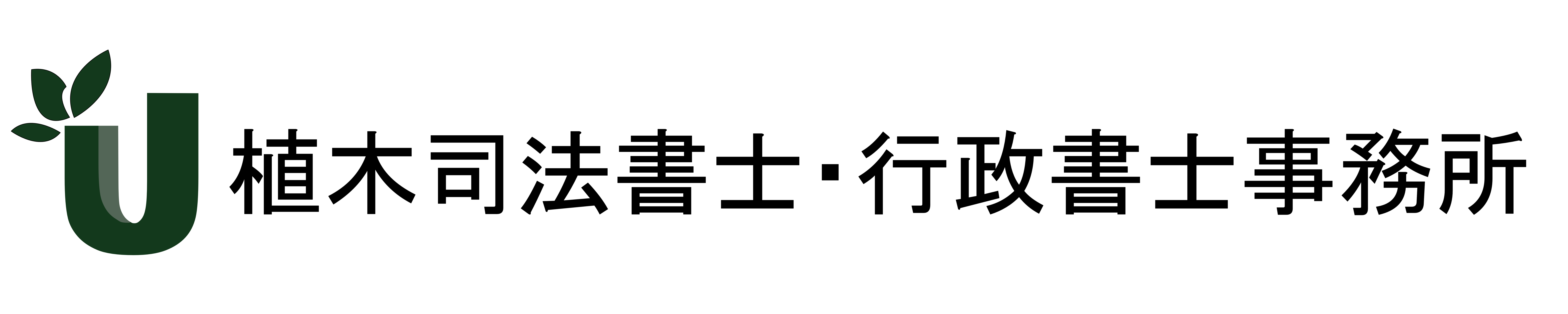業務一覧

まずはお気軽にご相談ください。
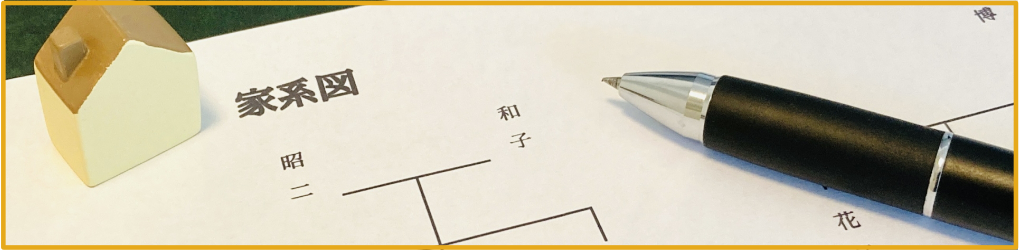
相続
亡くなられたご親族の方が所有していた不動産、預貯金などの相続手続き(相続登記、名義変更)についてご相談承ります。
- 相続登記(相続人への名義変更)について相談したい
- 相続手続きで困っている
- 相続を放棄したい
- 将来に向けての準備(遺言書作成、死後事務委任契約)
- 預貯金などの解約手続きを代行してほしい
令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上義務になりました。
遺産分割で不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が課される可能性があります。
令和6年4月1日よりも前に発生した相続でも義務化の対象になります。
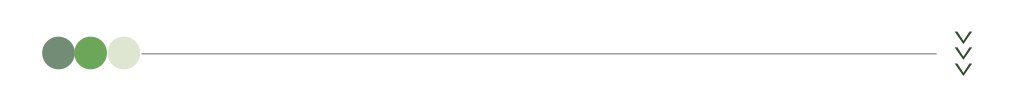
【相続について】 よくある質問Q&A
A:相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。

不動産登記
不動産の名義変更でも、様々なケースがございます。
- 不動産を相続人名義に変更したい
- 不動産を贈与したい
- 所有している不動産を売買した後、名義変更したい
- 住宅ローンを完済したので担保権を抹消したい
- 外国人名義の不動産を売買したい
不動産の状況によって、手続きの流れは異なってまいります。
一般的な左記ケースに該当した際は名義変更が必要となります
状況確認から行いますのでお気軽にご相談ください
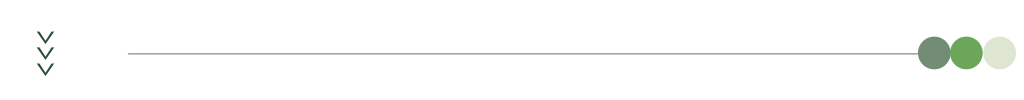
【不動産登記について】 よくある質問Q&A
A:住宅ローンの完済により、抵当権は当然効力を失います。ただ、登記記録上の「抵当権設定登記」は、自分で抹消登記手続きをしなければ、そのまま記載され続けることになります。
A:相続関係が複雑になっている可能性が多々あります。多数の相続人にあたる方と全員で遺産分割協議をする必要があり、協議が難航することもあります。専門家にお任せください。

後見
当事務所では後見の手続きや財産の管理などしっかりサポートさせて頂きます。
- 両親が認知症になったので対策を立てたい
- 医療、介護サービスの契約を代行してほしい
- 任意後見について相談したい
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない場合に、ひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援する制度です。
成年後見制度には、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれ、財産管理や身上保護を行う法定後見制度とあらかじめご本人自らが選んだ人に、ひとりで決めることが心配になったとき、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく任意後見制度があります。
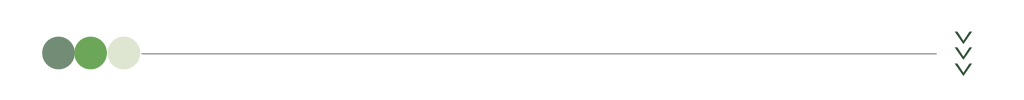
【後見について】 よくある質問Q&A
A:法定後見制度があります。相談から申立て手続き、その後のサポートまで当事務所がお手伝いします。また、将来の認知症になった時に備えて、ご本人がお元気なうちに、後見人となる人をご自身で事前に決めておく任意後見制度や、特定の財産のみをご本人の代わりに管理することを任せておく民事信託制度といった制度がございます。
A:家族がなる場合もあれば、専門職がなる場合もありますが、家庭裁判所が判断し、選任します。
A:無駄な支出を見直し、財産の収支を細部にわたって管理することです。また、家を売却するような局面でも、良心的、堅実なお取引を約束します。

商業登記
商業登記とは、法務局に重要な情報を登記する手続きです。
- 会社を設立したい
- 役員を変更したい
- 取引先に新株を発行したい
- 会社の資本金を増やしたいまたは減らしたい
- 会社を清算したい
- 会社の事業を親族に譲りたい
会社の情報に変更が生じた時は、必ず登記を申請することが法律で定めされています。登記期間は原則としてその登記の事由が発生した時から、本店の所在地においては2週間内とされています。
登記期間内に登記の申請を怠り、その後に申請をする場合であっても、登記申請は却下されることはありませんが、過料に処せられる可能性があります。
会社の設立から解散までの手続きについての法的なアドバイス、定款など登記に関する書類の作成の代行から登記申請まで一元的に当事務所は対応することができます。
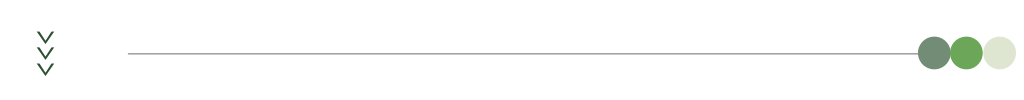
【商業登記について】 よくある質問Q&A
A:株式会社、一般社団法人など、役員が変更したときは役員変更の登記を申請する必要があります。株式会社の場合、役員の任期満了から2週間以内に役員変更登記をする必要があります。登記を怠った場合、裁判所から過料に処される可能性があります。
取締役が任期満了により退任し、時間的間隔を置かずに取締役に再任されたような場合にも、変更の登記が必要となります。
A:事業を始める際には法令上いくつかの手続きが必要になります。会社設立に際しての書類作成にあたっては、かなり複雑になりますので専門家が対応いたします。
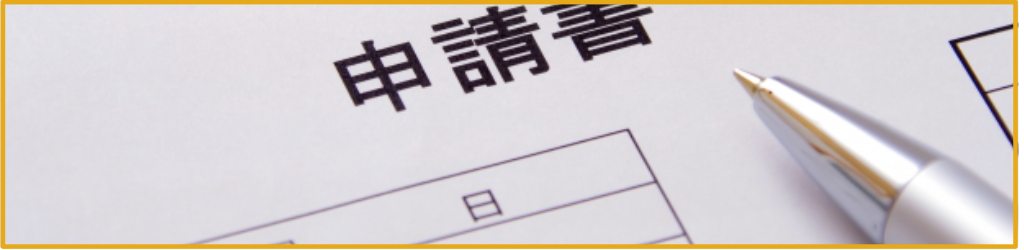
各種許認可
建設業許可、宅建業許可取得を行います。
- 建設業許可の取得をしたい
- 宅建業免許の取得をしたい
- 産廃業許可の取得をしたい
- その他各種の許認可の取得をしたい
建設業許可
建設工事は2つの一式工事と27の専門工事に分類されます。
それぞれの業種で専門工事の許可が必要になってきます。
事業内容をヒアリングしながら取得する業種を確定していきます。
宅建業許可
宅地建物取引業をを行うためには、宅地建物取引業法と言う法律に基づいた免許を取得しなけばなりません。
大臣免許や知事免許など、お客様と相談しながら進めさせていただきます。

【各種許認可について】 よくある質問Q&A
A:「知事免許」と「大臣免許」の2種類があります。
一つの都道府県の区域内のみに建設業の営業所がある場合には都道府県知事許可を
二つ以上の場合には国土交通大臣許可を受けることになります。
A:法人として新たに許可申請するものがあります。
A:建設業の経理作業は複雑になります。会計基準においても建設業独特の方法があります。
提携税理士や提携社会保険労務士を紹介させていただきます。

お客様に寄り添って様々な相談の解決をサポートします


06-6867-9130
受付時間:平日10:00~18:00
事務所概要
| 植木司法書士・行政書士事務所 |
| 住所 | 〒550-0006 |
| 大阪市西区江之子島1-7-3 | |
| 奥内阿波座駅前ビル203号 | |
| 阿波座駅 徒歩2分 | |
| TEL | 06-6867-9130 |
| FAX | 06-6867-9140 |
| Eメール | ueki-shoshi@kpd.biglobe.ne.jp |
| 受付時間 | 平日9:00~18:00 |